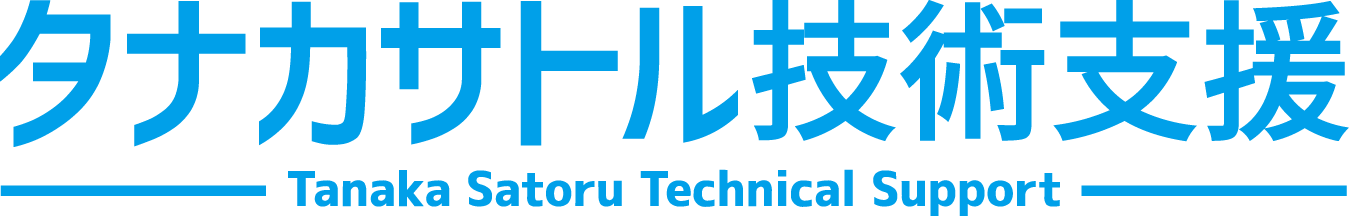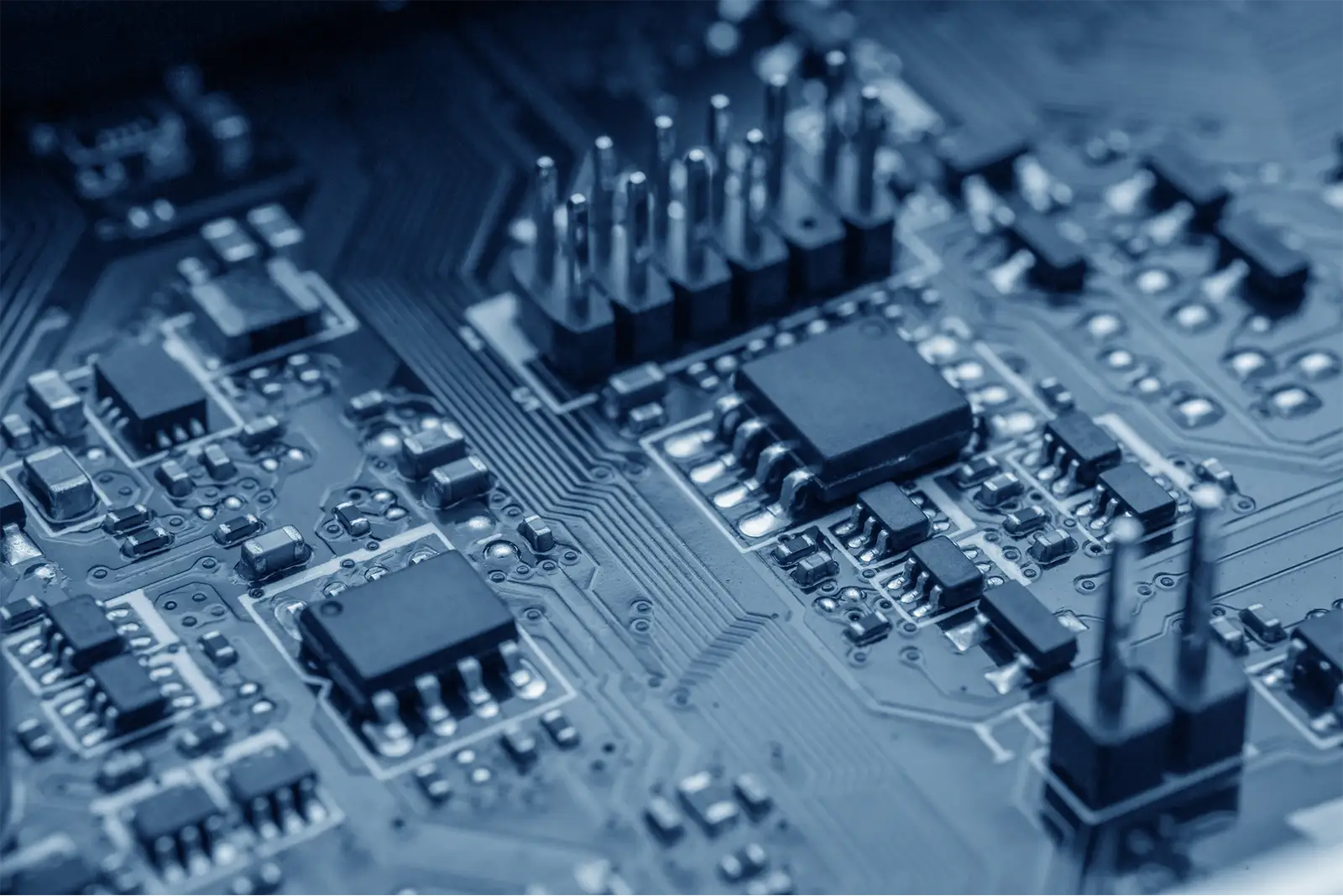電子回路部品を生産するある部門では、赤字採算の苦しい状況が続いていました。
工数が多く製品原価の労務費率が高いこと、お客様から大口の受注をいただけていないことが原因として考えられました。
そんな中、お客様より継続してリードタイム短縮の依頼があり応えられていなかったため、また、投資費用や場所の制約の中で改善を行うため、IE技術によるリードタイム短縮を課題として挙げ取り組みました。
特に工数の多いフォトリソ加工という工程を対象とし、15%の短縮を目標としました。
課題をクリアする上での問題点は次の4点でした。
- 対象が180工程以上あり、どこに問題があるのか把握できていない
- 作業者は長年の独自技術で仕事をする職人に近くなっており、変化をさせることに抵抗が強い。改善することは自分たちがやってきたことを否定されることだと思っている。
- リードタイム短縮は何度も取り組んでおり、技術者・作業者たちがこれ以上短縮できると思っていない.
- 工程の途中で他部署に依頼する部分もあり、自分達だけで改善をクローズすることができない。
問題点を解決していくため、次のように課題を挙げ対応していきました。
- 問題点の把握:どこでどれくらい生産に時間がかかっているのか
- 改善チームの意思の統一
- 改善に対するモチベーションアップ
- 他部門との連携
(1)問題点の把握:どこでどれくらい生産に時間がかかっているのか
現状把握をするため、どの工程で多くの時間がかかっているのかを調査することにしました。調査よりも対策実施を優先させる雰囲気がありましたが、それでは目標を達成できないと考えていました。
製品と一緒に工程を回るロットカードに加工開始/終了時間の記入欄を設け、作業者に記入してもらいました。
現場では常に小走りで次々と加工を行っていましたが、実際にデータを取ってみると1ロットの製品は投入してから出荷されるまでの約75%の時間は停滞している、置いたままになっていることが分かりました。
自分の想定をはるかに超え驚きました。
それまでは、加工の時間を短くすることに一生懸命に取り組んでいましたが、止まっている時間を改善することが何倍も効果があることが分かりました。また、停滞時間の工程によるばらつきは大きく、個別に原因調査が必要なことも分かりました。
(2)改善チームの意思の統一
製造・技術部門で改善チームを組み、最初の打合せから問題続きでした。
改善の目的を伝えたが、現場メンバーからは「俺たちがさぼっていると言うのか?俺たちの仕事が遅いと言っているのか?」とケンカ腰で詰め寄られました。言葉遣いは違っても、他のメンバーも同じように思っていることは分かりました。
技術的な不具合は原因をつかめば解決できますが、人間相手の交渉は本当に難しいと感じました。
現場に何度も足を運び、作業している様子を見て、困っていることや一生懸命仕事していることなどをよくヒアリングし、その上司にも状況をよく伝えるようにしました。週次の打合せ時には、それらを知りこれまでの長年の生産に対し感謝を伝えた上で、事業の現状や今後の厳しい状況を伝え協力のお願いをしました。
これらを繰り返し1ヶ月以上経ったたある日の打合せで、現場の年長者から発言がありました。
「自分たちの職場のことで、田中は一生懸命がんばっているじゃないか。自分たちの職場なんだから、自分たちでがんばろうじゃないか。」との発言で、少し間をおいて、出席者からは「わかった。協力するから何でも言ってくれ」との言葉が出て、現場の全面的な協力を得られる体制が作られました。
改善活動はスタートしたばかりでありましたが、とても感動し、感謝し、絶対に良い結果を出す!と思わされた日でした。
(3)改善に対するモチベーションアップ
現状把握のための時間調査と並行して、改善チーム内で提案を募りましたが、改善効果の小さい内容や、高額な機械を導入したいという難易度の高いものなど、費用対効果の小さい内容が多かったです。
提案で出された内容はできることから実施していくという前提で、私から違う方法の提案をしました。
(1)の時間調査の結果を都度集計して打合せで報告したところ、製品の停滞時間が非常に多いことが分かり、自分たちの努力とは別のところでいかにムダが多いかということに気付いてもらえました。
そして、思いついたことが優先でなく、一番時間がかかっていることから優先的に改善する必要があると伝えました。
まずは、停滞時間の長い上位5位までの工程について、考えられる理由を全て挙げてもらいました。それらを整理し問題構造図を使って「なぜなぜ」を繰り返し、真の原因は何かをみんなで考えました。現場メンバーの苦手な作業であり時間のかかる作業でしたが、重要な部分のためじっくり取り組みました。
最終的に問題の原因が明確になると、対策を立てるのは容易でした。
評価の時間や投資金額がかかる難易度の高い内容から、今すぐにできる内容まであり、優先度を決めて計画的に取り組むようにしました。現場メンバーに時間記録を継続してもらい、集計していくと、対策の効果が明確に出てきました。
それを報告し、関わった人たちを褒め、自分たちは改善していけるチームだと共感しあいました。「ああしたらいいんじゃないか」「こうしていいか?」など、新しいアイディアや前向きな発言を多くもらえるようになりました。この頃から、まだ対策立案状態で実施していない内容についても停滞時間が改善しているのことが見受けられました。
作業者の意識が前向きになり細かい気遣いをした結果だと考えられます。
うまくいった内容は適時ルール化・文書化を行い、元に戻らないための歯止めとしました。
また、これらにつられて製品の歩留りも改善していきました。
作業者の気持ちが、よい仕事をしたい、よい製品を作りたいと前向きになったことで、製品をより大事に扱うようになったのではないかと思います。
(4)他部門との連携
加工全体の中には自部門で機械を持っていない工程もあり、他部門との製品のやり取りが何度も発生します。
他部門の中においては、お客様からの依頼という意識は薄く、自分たちの仕事で手一杯のため、こちらが依頼した仕事は優先度を下げられることが多かったです。
なぜ改善活動をしているかの理由、今後の伸ばしたい方向性などについて説明し、何をしたら優先度を上げてもらえるかを聞き、こちらもできるだけことをするので協力してくださいという姿勢でお願いをしていきました。
他部門の作業者も、お互いメリットがあるならということで快く引き受けてくれました。
製品をやり取りする際の内容については歯止めのルール化を行い、メンバーもルールを守るようにしました。
このようにしてたくさんの課題をメンバーと協力し前向きに解決していき、次のような成果を得ることができました。
時間調査から真の原因を探り、優先度を決めた多くの対策を計画的に実施し、目標以上のリートタイム20%短縮を達成することができました。後日、納期のため競合に取られていた中量の製品を受注することができ、少量と比べ採算性のよい製品の割合が増えたことで赤字部門から一気に黒字化を進めることができました。
関連部門のメンバーや責任者からは次のような感想をいただきました。
- 注文が取れず長い間苦しい状況だったが、黒字化できて現場の苦労も報われる。
- 自分たちがここまで大きく成長できるとは思わなかった。
- 製品が流れやすくなって、いつもバタバタしていた生産管理がうまくできるようになった。
- 現場のいろいろなやりにくいことを解決してくれて仕事をしやすくなった。
最後に、これらの活動を通して私が学び実践したポイントを挙げておきます。
これらからヒントを得て、事業を進める中で何かのお役に立てれば幸いです。
- 思い付きで改善活動をすると負担が増え、効果も分からず形式だけになってしまう。何をすればよいのかを最初にしっかり見極めて進めれば必ずよい結果を出せる。
- 「人を動かす」ためには承認欲求を満足させること言われるが、正に実践で経験することができた。
- 人が前向きな心理状態で仕事をする時、その効果は予想より大きく、結果は数字としても明確に表れることが分かった。