人手不足が続いている建設業では、応募者が少なかったり希望する人材と出会えなかったりなどの理由で採用が進んでいません。
離職率の高い企業では、その悩みは一層顕著になっています。
本記事では、人手不足が続いている企業に向けて、人手不足が続く理由と対策について解説します。
ICT化のメリットと導入事例も紹介するので、業務の効率化を目指している企業は参考にしてみてください。

建設業界の現状

人手不足が続いている建設業界は、以下のような問題を抱えています。
- 建設業界全体で就業者数の減少と高齢化が進んでいる
- 建設業の有効求人倍率が上昇している
それぞれの問題について、詳しく解説していきます。
建設業界全体で就業者数の減少と高齢化が進んでいる
建設業界における就業者数の減少は深刻な問題です。
厚生労働省の資料によると、令和3年の就業者数は約485万人で、ピーク時の約685万人から200万人ほど減少しています。
高齢化によって退職するベテランが増える一方で、若い世代の就業率が伸び悩んでいるのが原因です。
その結果、現場での作業者不足を招き、業務の遂行に必要な人材の確保が困難になっています。
(引用:厚生労働省「建設投資、許可業者数及び就業者数の推移」)
建設業の有効求人倍率が上昇している
建設業界では、有効求人倍率が年々上昇しています。
厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和5年5月分)について」では、パートを除いた建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は5.92倍になりました。
同月の一般職業紹介状況での有効求人倍率は1.23倍だったので、建設業の人手不足が顕著になっていることがわかります。
建設業界の有効求人倍率が増加している背景には、体力を要する仕事や労働環境の改善が不十分なイメージが浸透していることが原因として考えられます。
(引用:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年5月分)について 参考統計表」)
建設業界の人手不足の理由

建設業界では年々人手不足が深刻化しています。
建設業界で人手不足が進んでいる理由は、以下の通りです。
- 外国人労働者の減少
- 定着率の低さ
- 給与アップが見込めない
- 建設需要の増加
外国人労働者の減少
建設業界では外国人労働者の活用が進んでいましたが、近年は外国人労働者の数が減少しています。
円安により、日本国内の賃金が低下していることが原因です。
外国人労働者にとっては、日本で働くよりも東南アジアやアメリカで働いた方が給料は多く貰えるので、季節労働者そのものが減少しています。
外国人労働者が減少することによって建設現場の人手不足が加速し、作業効率に影響を与えています。
定着率の低さ
建設業界における労働者の定着率の低さも大きな問題です。
新たに採用された労働者が早期に離職するケースが多く、採用コストだけが膨らんでしまうという悪循環が生まれています。
定着率が低い理由には、労働条件や給与の問題、仕事の厳しさなどが影響しています。
採用しても短期で離職されてしまうので、企業は慢性的な人手不足が続いているのが現状です。
給与アップが見込めない
建設業界における給与の低さは、業界全体への魅力低下を招いています。
労働者は安定した収入アップを求めていますが、社会保障の増加や材料費の高騰が原因で給与がアップされないのも人手不足の要因です。
働き方改革によって労働時間の見直しが進んでいることも、給与減少の一因です。
建設需要の増加
近年の建設業界は、都市化やインフラの更新、新たな建築ニーズの増加などで建設需要が増加しています。
また、東京オリンピックでの建設ラッシュや東日本大震災の復興なども建設需要が増加した理由の1つです。
建設需要の増加は、業界にとっては明るい話題ですが、人材確保という大きな課題をもたらしています。
高度経済成長期に建設された建物やインフラの改修も増加しているので、建設業界では需要を満たすための人材確保が急務となっています。
建設業界が人手不足を解消するための対策

建設業界が人手不足を解消するためには、以下のような対策が必要です。
- 労働環境と待遇の改善
- 採用手段の多様化
- 業務効率化の推進
- イメージアップのための情報発信
- 外国人労働者の積極採用
それぞれの対策について、詳しく解説していきます。
労働環境と待遇の改善
建設業界における労働環境と待遇の改善は、人手不足解消のための最優先課題です。
労働時間の見直しや安全管理の徹底、そして競争力のある給与体系の導入が必要です。
労働者の高齢化とともに、若い世代の建設業への関心は薄れています。
労働環境と待遇の改善は、他業種の人材にとって魅力をもたらし、人材の確保と定着率の向上につながります。
また、働き方改革を進めて、労働時間の短縮やフレキシブルな働き方の推進も必要です。
労働環境と処遇の改善は、建設業のイメージを向上し、多くの人材を引き付けるでしょう。
採用手段の多様化
建設業界が採用手段を多様化することで、人手不足の解消が期待できます。
従来のハローワークや求人サイトでの採用方法に加え、以下のようなアプローチを取り入れてみましょう。
- SNSでの採用呼びかけ
- 自社サイトでの魅力発信と採用
- Youtubeなどの動画で社風を伝える
若い世代には、SNSやYoutubeなどで企業の特徴を理解することで、応募へのハードルが下がります。
求人サイトに給与や雇用条件を記載するだけでは、求職者は関心を示さなくなりつつあります。
採用手段を多様化することで、これまで接点を作れなかった他業種の人材へのアプローチが可能です。
業務効率化の推進
業務効率化は、限られた人員で最大限の成果を上げるために不可欠な対策です。
ITツールやデジタル技術を積極的に導入することで、作業の効率化が図れます。
建設現場の管理システムのデジタル化やドローンを活用した点検や測定は、作業時間の短縮と同時に安全性の向上も期待できます。
ITツールやデジタル技術を活用することで、労働者一人ひとりの負担を軽減し、より多くの作業を少ない人員でまかなえるようになるでしょう。
イメージアップのための情報発信
建設業界全体のイメージアップは、新たな人材を引き付けるために重要です。
インフラの整備や住宅の提供など、社会貢献度の高い建設業の仕事に対する認識を高めるためには、積極的な情報発信が必要です。
建設業の現状や仕事の魅力、キャリアパスの可能性を社会に広く伝えることで、特に若い世代の興味を集められるようになるでしょう。
情報を発信する際は、テキストだけでなく、画像や動画の活用が有効です。
外国人労働者の採用
国際的な労働力の活用も、人手不足解消のため有効な手段です。
外国人労働者を採用するためには、ビザの規制緩和や適切なサポート体制の構築が必要です。
企業全体で多文化を受け入れる体制を整備し、外国人労働者が日本の建設現場で働きやすい環境を作ることが求められています。
差別のない職場を作ることで多様な人材を確保し、競争力の強化にもつながります。
以下の記事では、建設業での人材確保や人材育成について詳しく解説していますので、こちらも合わせて参考にしてください。

建設業界の人手不足を解消するための行政の対策

建設業界の人手不足を解消するために、行政も以下のような対策を講じています。
- 処遇の見直し
- 効率化による生産性の向上
- 残業の規制
- 36協定
- 建設キャリアアップシステム
自社に導入できるように、それぞれの対策を解説していきます。
処遇の見直し
建設業界の労働者に対する処遇の見直しは、人手不足解消のための重要なステップです。
下請け労働が一般的な建設業界では、社会保険に未加入の企業も存在します。
社会保険の加入は、労働者の怪我や病気の際の保障や老後の年金を充実させるための制度です。
この社会保険に未加入の企業には、建設の許可や更新を認めない新しい仕組みが作られています。
また、技術研修やパトロール、個別指導を行って労働者が安全に働ける環境を整えています。
効率化による生産性の向上
生産性の向上は、限られた人材で最大限の成果を得るために重要です。
日本では、古くから長時間労働を美徳とする文化が根付いています。
生産性を向上するためには、長時間労働を是正し、限られた時間と人材で最大限の成果を出すための施策が必要です。
そのためには、ITツールの導入やデジタル化の推進が欠かせません。
建設現場における業務のデジタル化は、労働時間の短縮と効率化につながり、人手不足に有効な対策となります。
建設業の生産性が低い原因や、生産性を向上させる方法については以下の記事で詳しく解説しています。
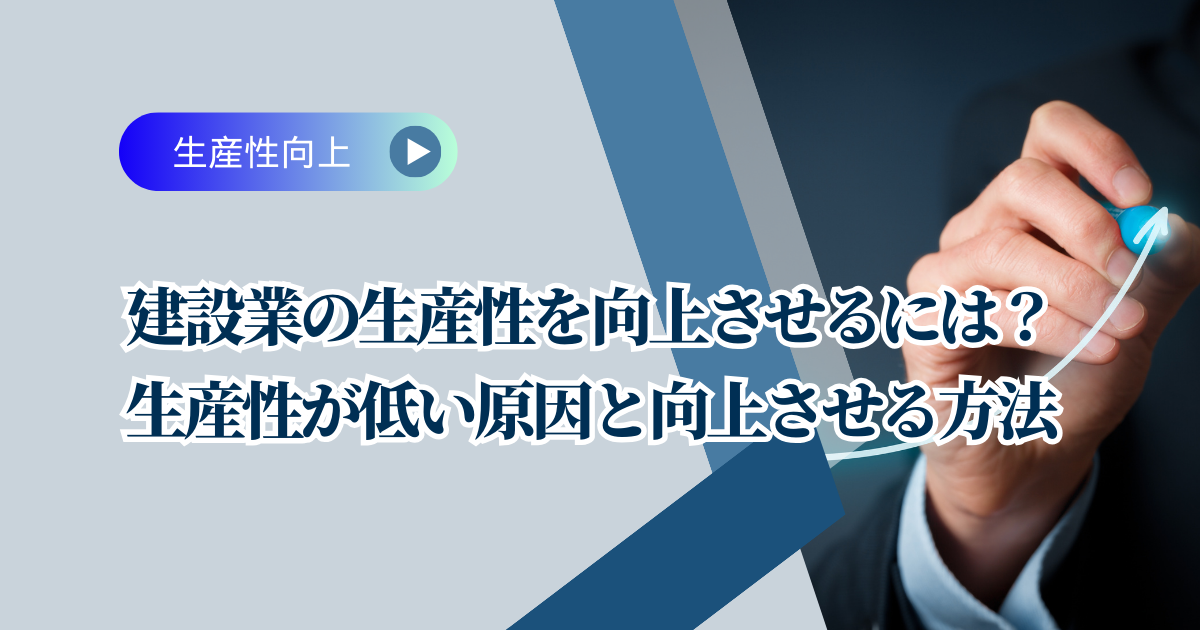
残業の規制
2024年4月1日から、建設業にも時間外労働の上限規制が設置されます。
これまでの建設業界では、36協定を締結していれば時間外労働をしても罰則はありませんでした。
しかし、2024年4月1日からは月45時間、年360時間の時間外労働に納めなければ罰則の対象となります。
残業の規制を通じて労働時間を合理化することで、労働環境の改善が期待されています。
行政による残業規制は、多くの企業が取り入れなければいけないので、働きやすい業界という新しいイメージ創出ができるか注目が集まっています。
36協定
36協定は、労働基準法第36条に規定されている「会社と労働者代表による、残業に関する合意書」です。
36協定を結ぶことで、以下のような働き方ができました。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」~「6カ月平均」のすべてが1カ月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月まで
これまで行政は、36協定を締結した企業に対しては上記の働き方を容認していました。
しかし、働き方改革が推進される現代では、36協定は採用時の大きな懸念点となっていることから、規制の対象にしています。
建設キャリアアップシステム(ConstructionCarrerUpSystem)
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みです。
建設キャリアアップシステムの導入には、以下のようなメリットがあります。
- 労働者のキャリアの見える化
- 経営者と事務作業の負担軽減
労働者は自身のキャリアとスキルを提示できるので、より高い賃金を得る機会が生まれます。
行政は、建設キャリアアップシステムの普及と支援を行い、建設業界でのキャリア形成を促進しています。
建設業の生産性向上とICT化

建築業が生産性を向上するためには、ICT化も必要です。
- ICT化は情報通信技術の活用
- 建設業にICT化が求められる理由
- ICT化の具体例
- ICTを導入するメリット
上記を解説することで、ICT化を進める理由が理解できるでしょう。
ICT化は情報通信技術の活用
ICT(Information and Communication Technology)化とは、情報通信技術を活用して業務の効率化や生産性の向上を図ることです。
建設業界においては、ITツールやソフトウェアを用いてコミュニケーションを図ったり作業プロセスを改善したりすることを意味します。
ICT化によって建設現場での情報共有が迅速化され、計画と実行の精度が高まります。
また、労働環境の改善や安全管理の強化も可能です。
建設業にICT化が求められる理由
建設業界におけるICT化は、現在の労働環境や若い世代の要求に応えるために不可欠な対策です。
これまでの建設現場では、人的資本があったので効率化を進める必要がありませんでした。
しかし、高齢化に伴う労働力の減少や若い世代の採用競争の激化により、効率的で安全なプロジェクトの実施が求められています。
ICT化によって、業務の効率化と安全を両立し、生産性の向上を実現できます。
ICT化の導入事例
具体的なICT化の導入事例を紹介します。
- ドローン
- プロジェクト管理ツール
ドローンを用いた測量や監視は、作業の効率化と安全性を両立してくれます。
人が測量するには危険な場所も、ドローンを使えば安全に行えるでしょう。
プロジェクト管理ツールの導入は、スケジュールを見える化することで工期を守りつつ、人材を最適に活用しやすくなります。
プロジェクト管理ツールは共有が容易なので、現場や事務所を問わずに全ての関係者間での情報共有と進捗管理がスムーズになります。
ICTを導入するメリット
ICTの導入には、以下のようなメリットがあります。
- ヒューマンエラーの軽減
- 安全性の確保
- 円滑なプロジェクト進行
- トラブルの際の迅速な対応
ドローンを測量に活用することで、ヒューマンエラーの軽減と安全性の確保ができます。
現場の状況を問わずに測量ができるので、競争の優位性も保てるでしょう。
また、リアルタイムでスケジュールを共有することで、問題の早期対応が可能となり、プロジェクトのリスク管理が強化されます。
労働者の安全を確保しつつ作業環境を改善できるので、従業員の満足度と定着率が向上します。
ICTの導入は、建設業界の長期的な成長と競争力の維持に不可欠です。
こちらの記事では建設業でのDX導入について詳しく解説していますので、ぜひ合わせて参考にしてください。

就活生が建設業に求めていること

これから社会に出る就活生の採用は、建設業界にとって大きな課題です。
1人でも多くの就活生を採用するためには、就活生が求めていることを理解する必要があります。
- 就活生は情報を求めている
- 就活生はインターンシップを求めている
- 就活生と建設業のマッチング
それぞれの項目を解説して、就活生が建設業界に求めていることを理解しましょう。
就活生は情報を求めている
建設業界に関心を持つ就活生たちは、まず業界に関する詳細な情報を求めています。
特に重要なのは、業界の現状や仕事内容、キャリアパス、そして建設業界の将来性です。
就活生が情報を取得するためには、企業は自社のサイトやソーシャルメディアを活用して、業界の魅力や仕事のリアリティを伝えることが重要です。
また、若い世代が関心を持ちやすいように、建設業界のイメージ向上に努める必要があります。
企業と教育機関が連携して定期的なセミナーやワークショップを開催することも、就活生に対してポジティブな情報を提供するためには効果的です。
就活生はインターンシップを求めている
就活生たちは、インターンシップを通じて業界を理解したいと考えています。
インターンシップとは、就業体験のことです。
実際に建設現場に赴いて仕事内容を学び、実務経験を積むことで入社するか否かの判断ができるためです。
企業は、就活生に対して実践的なインターンシッププログラムを提供し、若い人材が業界に興味を持ちやすい環境を作る必要があります。
インターンシップは、就活生にとってキャリアの選択肢を広げるだけでなく、企業にとっても将来の優秀な人材を確保する絶好の機会です。
建設業界のインターンシップを経験した就活生が後輩にその経験を伝えることで、より多くの学生が建設業界の課題や魅力を理解できます。
就活生と建設業のマッチング
就活生と建設業界との間で良いマッチングを実現するためには、双方の積極的なコミュニケーションが必要です。
コミュニケーションを重ねることで、企業は学生の興味や能力を理解し、適切な労働環境を提供できるようになります。
また、建設業界の企業は、就活生に正確かつ魅力的な情報を提供することが重要です。
こうした取り組みにより、就活生は自分のキャリアに合った建設業界の企業を見つけることができ、企業も優秀な若手人材を確保することが可能です。
建設業界の人手不足対策には環境改善とICT化が重要

建設業界の人手不足を対策するためには、労働環境の改善とICT化の推進、そして若い世代や外国人労働者の積極採用が有効です。
行政も建設業界の人手不足解消に向けて、残業の規制を強化したり、社会保険未加入の企業の建設許可を認めなくなったりという対策を講じています。
行政と企業が連携して、深刻化する建設業界の人手不足対策を進めることが重要です。
採用を強化しつつ、離職を予防するための対策にも力を入れて安定した雇用を維持していきましょう。
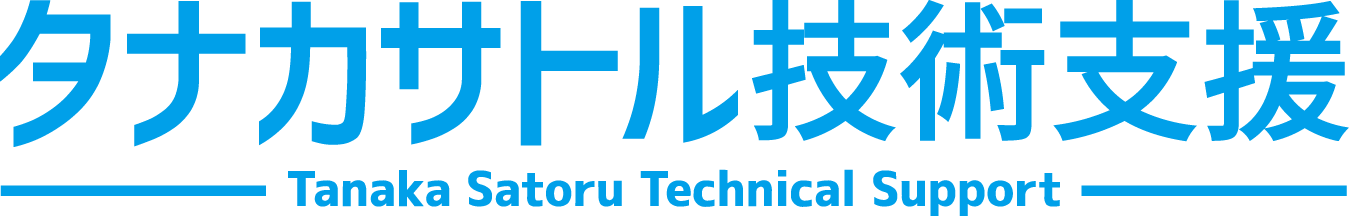


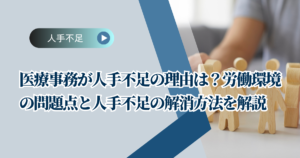

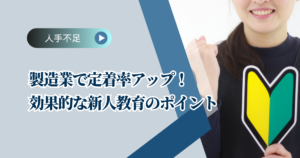
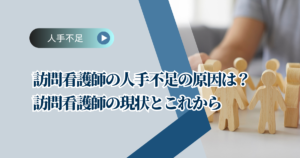
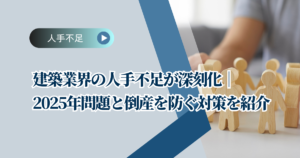
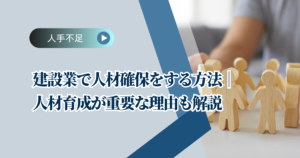
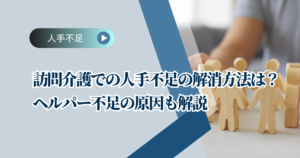
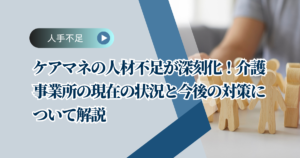
コメント