少子高齢化が進んでいる日本では、若手の労働力の確保が難しくなっています。
若手の人材を採用しても、短期離職してしまったり仕事を任せられなかったりといった問題があります。
そのため、建設業界では若手の人材育成が急務です。
今回は、建設業が抱える人材問題と、若手の人材育成のポイントを紹介します。
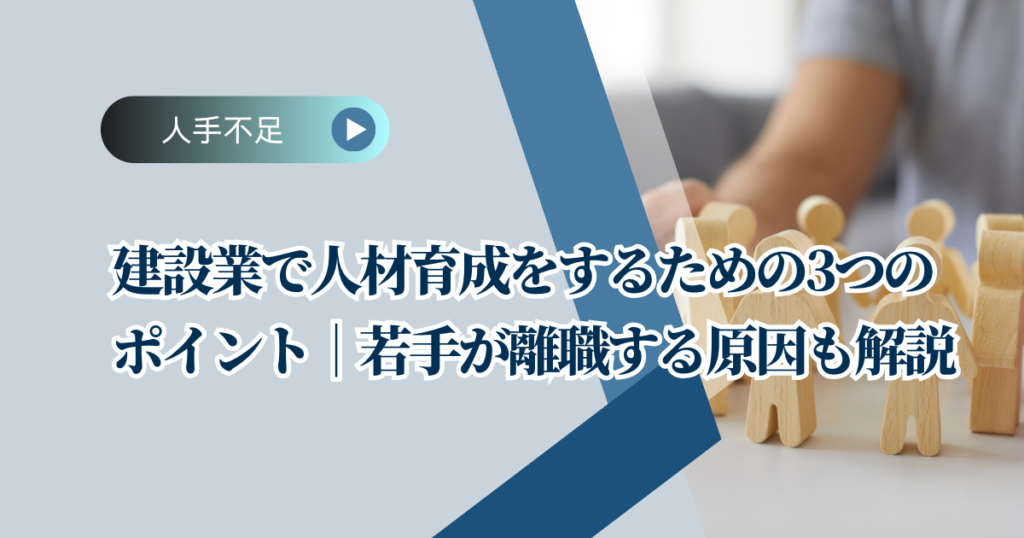
建設業が抱える人材問題

建設業が抱える人材問題には、以下のような事例があります。
- 若手人材の減少
- 若手の人材が離職していく原因
それぞれの問題について、詳しく解説していきます。
若手人材の減少
若手人材が減少している原因は、新規参入しようとする若手の就業者そのものが減少しているためです。
国土交通省のデータによると、令和3年の建設業就業者の割合では55歳以上が35.5%、29歳以下は12.0%という結果でした。
建設現場では3人に1人が55歳以上なのに対して、29歳以下は10人に1人の割合しかいません。
少子高齢化が進んでいる日本では業種を問わずに就業者の高齢化が進んでいますが、建設業では高齢化が顕著になっています。
若手人材の新規参入が少ない理由には、就業者の減少だけでなく業界全体のイメージも影響しています。
建設業は「きつい・きたない・きけん」という3Kが根付いているため、ホワイトな企業を求める若手人材から敬遠されているのが現状です。
若手人材が離職していく原因
若手人材を採用しても、短期離職されてしまうと企業にとっては大きな痛手です。
若手人材が短期離職してしまう原因は、以下の通りです。
- 職場での人間関係
- 仕事へのプレッシャー
建設業界では、1つの現場を数か月や数年かけて担当します。
その間は、仕事上の人間関係は現場監督や一緒に働く作業員に限定されます。
長年建設業に携わっている人は職人気質な人が多いので、丁寧な指導ができなかったり気難しかったりも珍しくありません。
建設現場で人間関係が合わないと、仕事そのものが苦痛に感じやすいので離職してしまいます。
また、建設現場では工期が最優先されるため、進捗が遅れると残業や休日出勤で対応しなくてはいけません。
常に工期を気にしながら作業していくことが若手人材にはプレッシャーになってしまい、離職を選んでしまうケースもあります。
建設業界の人手不足については、以下の記事でも詳しく解説しています。

建設業が若手人材を育成するためのポイント

建設業が若手人材を育成するためには、以下のようなポイントがあります。
- 若手人材の気持ちや考えを理解する
- 仕事を丁寧に教える
- 今後のキャリアプランを考える
特に、若手人材の気持ちや考えを理解することが、人材育成では大切です。
若手人材の気持ちや考えを理解する
若手人材を育成するためには、怒らずに相手を理解することから始めます。
今の若手は家や学校で怒られる機会が少ないので、叱責に弱いという特徴があるためです。
相手の得意なことや不得意なことを踏まえながら現場で指示を出しましょう。
丁寧なコミュニケーションを心がけることで、若手人材の積極性を引き出せるようになります。
伝えたいことを丁寧に伝えることで、若手人材の育成が可能になるでしょう。
仕事を丁寧に教える
一昔前は背中を見て学ぶ、技術は盗むのが当たり前でしたが、現代ではそれは通用しません。
若手人材を育成するには仕事を丁寧に教えることを意識しましょう。
今の若手は、作業する前になぜこの作業が必要なのか、どういう注意点があるのかを知りたがる傾向があります。
忙しいからと作業の指示だけしても、若手は気持ちよく仕事ができません。
丁寧に作業の意味や注意点を伝えることで、若手人材は作業を丁寧に行ってくれます。
また、若手人材は次に何をしていいか分からない時に、普段から怒っている上司や監督に指示を仰ぐと大きなストレスを感じます。
普段からコミュニケーションを大切にしておくことで、作業が円滑に行えるでしょう。
今後のキャリアプランを考える
若手人材にとって大切なのは、今後のキャリアプランです。
5年後や10年後のキャリアプランを作成することで、日々の仕事へのモチベーションも向上します。
将来が見えない状態で日々の現場仕事を続けるのは、安定を求める若手人材にとってマイナスな要素です。
本人の希望や適性を考慮しながら、最適なキャリアプランを考えてみましょう。
建設業の人材育成に向けた国土交通省の取り組み

国土交通省は、建設業の人材育成に向けて以下の取り組みを行っています。
- 人材確保
- 人材育成
- 魅力ある職場づくり
それぞれの取り組みを自社に反映するために、詳しく解説していきます。
人材確保
国土交通省は、建設業への入職や定着を促すために以下のような予算編成をしています。
- 建設産業の働き方改革の実現:185 百万円
- 建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業:550 百万円
- 建設事業主等に対する助成金による支援:76.4 億円
建設業は過酷というイメージを払拭するためには、働き方改革を積極的に導入して若手人材が働きやすいと感じる環境を作ることが大切です。
35歳未満の若手人材や女性を試行雇用した際や女性専用作業施設を整備した建設事業主には、助成金を支給することが決まっています。
助成金を活用しながら、若手人材を積極的に採用してみましょう。
参照:国土交通省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます」
人材育成
人材育成分野では、以下のような予算編成になっています。
- 建設産業の働き方改革の実現(再掲):185 百万円
- 建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業(再掲):550 百万円
- 中小建設事業主等への支援(建設労働者育成支援事業等):4.8 億円
建設労働者育成支援事業では、建設業の無料職業訓練を実施しています。
無料ながら、建設業に欠かせない以下の資格取得を目指せます。
- 玉掛け技能講習修了資格
- 足場の組立て等特別教育修了資格
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了資格
- 高所作業車運転技能講習修了資格
他にもさまざまな資格取得ができるので、これから建設業界で働きたいと考えている若手人材の育成が期待されています。
参照:国土交通省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます」
魅力ある職場づくり
魅力ある職場づくりでは就労者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備に向けて以下のような予算編成を行っています。
- 建設産業の働き方改革の実現(再掲):185 百万円
- 建設業許可の申請手続き等の電子化の推進:115 百万円
- 働き方改革推進支援助成金による支援:68.4 億円
- 働き方改革推進支援センターによる支援:36.7 億円
具体的には、以下のような取り組みを推奨しています。
- 労働条件の見直し
- 職務内容の見直し
- 人材育成制度の充実
特に労働条件の見直しでは、給与の見直しや社会保険の適正加入など、就労者の生活に直結する取り組みが多数記載されています。
参照:国土交通省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます」
建設業の人材育成とDX

建設業の人材育成では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることも効果的です。
若手人材はDXに関わるツールに強いという特徴を持っているので、その知識やスキルを現場で活かすことで仕事へのモチベーションを維持し、作業効率化にもつながります。
ドローンやロボットを導入することで危険な作業を効率化し、限りある人材を有効に活用できます。
若手人材にドローンやロボット操作を学ばせることで、新たな技術の習得とリソースの最適化が可能です。
以下の記事では、建設業のDX化について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:建設業の人材育成は企業全体で行おう

建設業では、若手人材の不足が著しく問題になっています。
若手人材を育成するためには、組織全体でコミュニケーションを円滑に行い、一つひとつの仕事を丁寧に教える環境を作りましょう。
どれだけ業務を効率化しても、働いている従業員の意識改革をしていかないと若手人材は育ちません。
企業が一体となって若手人材の育成と業務改革に取り組んでいきましょう。
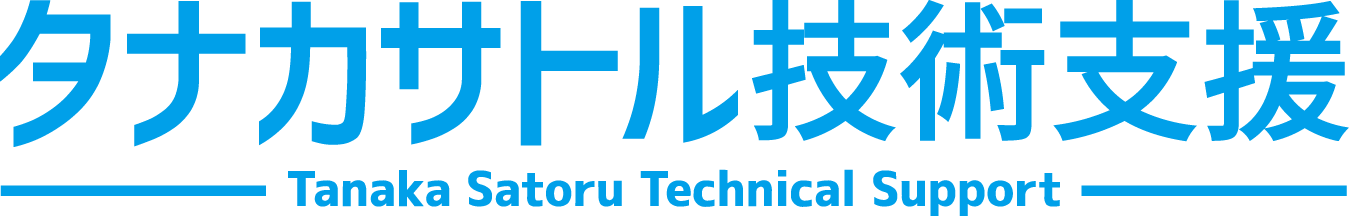


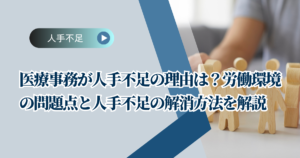
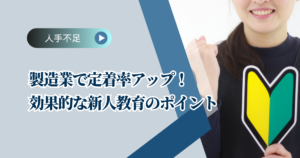
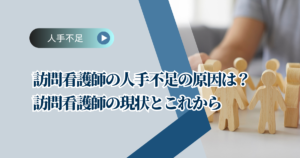
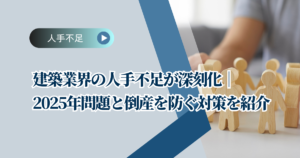
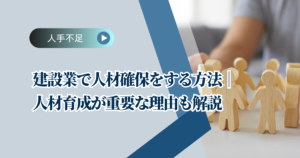

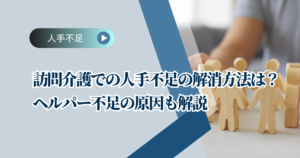
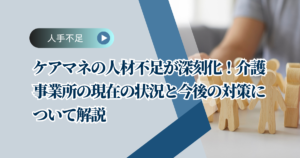
コメント